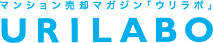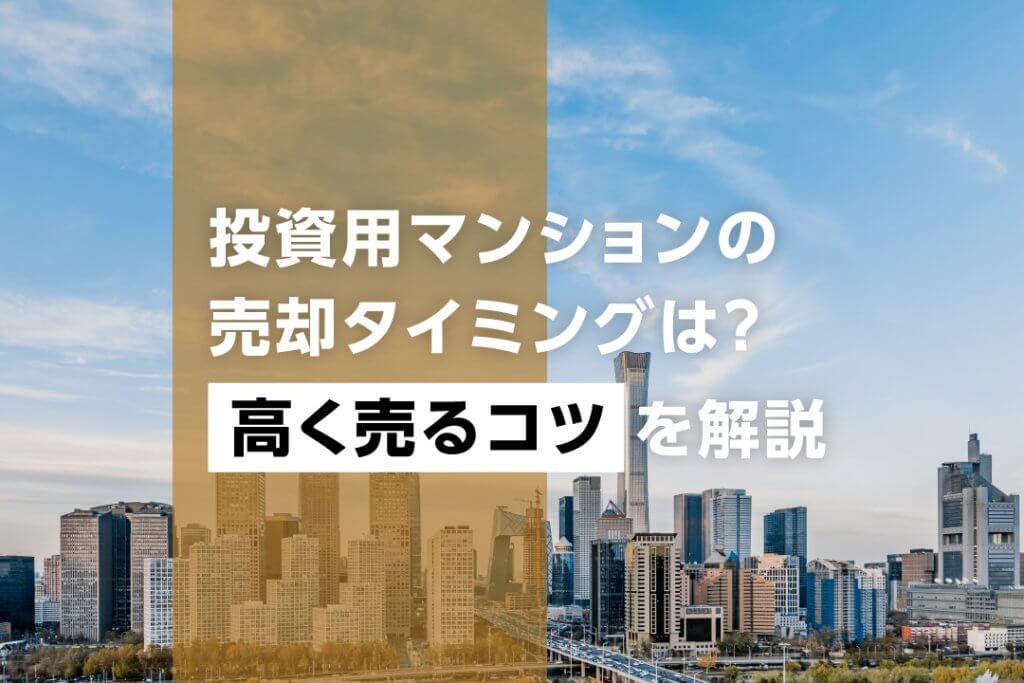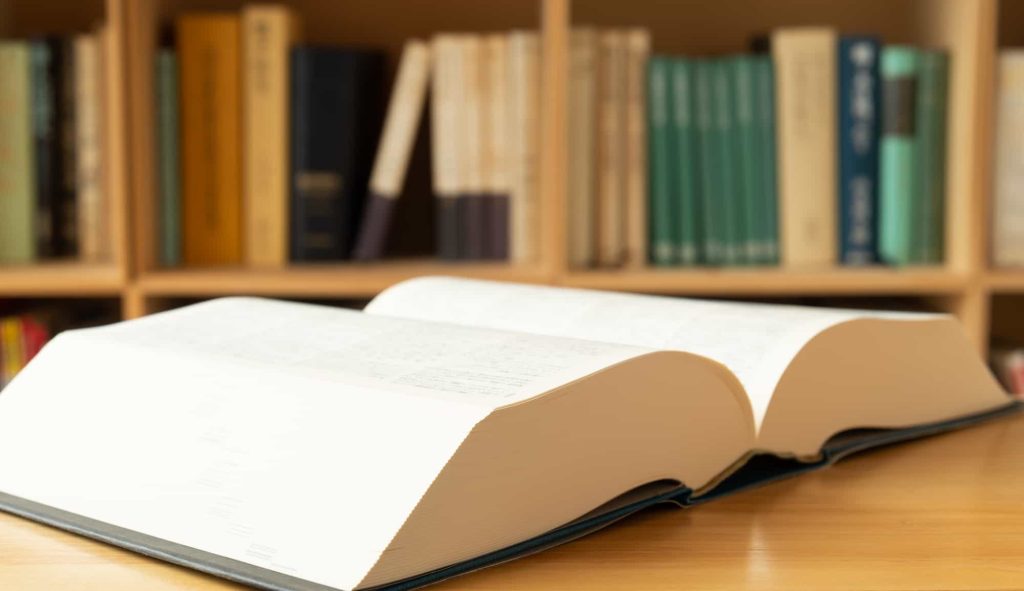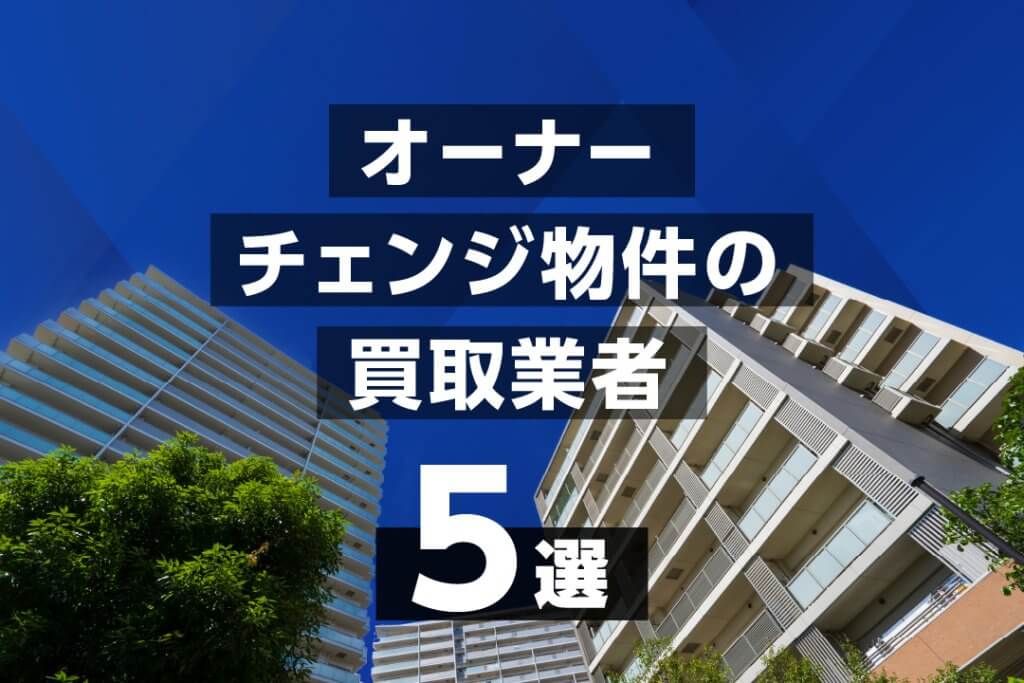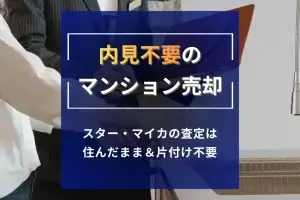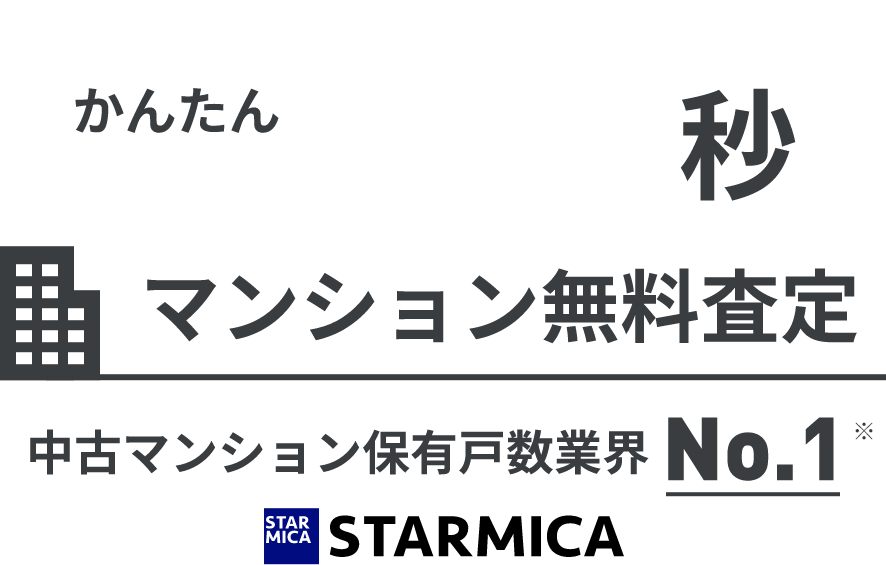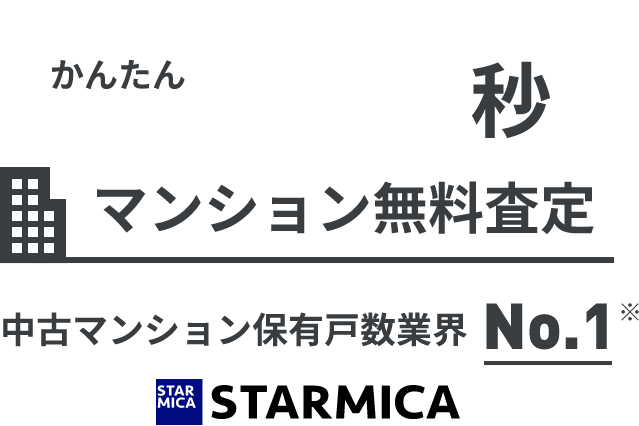オーナーチェンジのお役立ち記事まとめ
オーナーチェンジとは
オーナーチェンジ物件とは、賃貸中の収益物件のことです。
借主が入居中のまま売買されるため、買主は基本的に室内を見ずに購入することになります。
所有権だけでなく賃貸人の地位も承継されることから、売買では特有の注意点があります。
オーナーチェンジの基本
オーナーチェンジは、売買に伴い賃貸借契約をそのまま引き継ぐ売買形態です。
売主には高く売るためのポイントがあり、買主には注意すべきポイントが存在します。
買主としては売主のよくある売却理由も把握しておくことが望ましいです。
オーナーチェンジ物件の売却・購入のタイミング
オーナーチェンジ物件には、売却に適したタイミングが存在します。
高く売れる時期は買主にとってもローンを組みやすい時期でもあり、売りどきは買いどきでもあります。
売買は、適切なタイミングを見定めることがコツです。
オーナーチェンジの収益性と投資戦略
オーナーチェンジ物件は、収益性に基づいて価格が決まります。
適切な価格を見極めるには、利回りの知識も必要です。
また、オーナーチェンジ物件は購入後に収益を向上させることもできます。
家賃を上げる交渉方法も知っておくと購入後に役立ちます。
オーナーチェンジの契約や手続き
オーナーチェンジ物件の売買では、敷金の精算や賃貸人の地位承継通知といったマイホームの売買には見られない独自の契約手続きが存在します。
また、家賃収入に関する確定申告の手続きも知っておくことが必要です。
関連記事

オーナーチェンジ時の敷金の扱いとは?賃貸中の承継トラブル回避のポイント
一般的な売買契約や相続など、不動産を取得する方法はいくつかあります。 その売買契約の中でも、賃借人がいる状態で売買を行われるのがオーナーチェンジです。 買主にとっては、物件の引渡しを受けた

【雛形・テンプレート付き】オーナーチェンジ時に賃貸人変更通知書を発行する手順と記載内容
賃貸中の投資用マンションの売却を検討しているけど、そのことを賃借人に知られたくないという人も多いのではないでしょうか。 賃貸物件の売却を検討している段階では賃借人に知らせる必要はありません。

投資用マンションで不動産投資をしているサラリーマンや投資家向けの確定申告
サラリーマンや投資家の方でマンションやアパートなどの不動産投資をしている人は、確定申告について気になっている方も多いと思います。 確定申告の内容は自己申告ですので、知識をきちんと備えれば節税も可
オーナーチェンジのトラブル・リスク管理
オーナーチェンジ物件には借主が入居中であることから、借主による入居者トラブルも想定されます。
場合によっては立ち退き交渉が必要になるかもしれません。
立ち退きに関する知識も知っておくと、心強いです。
収益物件の買取会社一覧と選び方
収益物件を早く売りたいときは、買取がおすすめの売却方法となります。
買取で少しでも高く売るためには、複数の不動産会社に査定を依頼することが必須です。
査定は、あらかじめ地域の中で買取に強い会社を調べたうえで依頼することがコツとなります。
関連記事

オーナーチェンジ物件の買取業者5選!エリア別のおすすめ不動産会社も紹介
不動産投資を始めて、マンションを賃貸してきたけど、「今の物件は利回りが悪い。もっとよい収益物件に買い替えたい」「高齢で物件の管理が面倒になってきた。引退したい」「とにかく急いで現金化したい」という方も

東京で収益物件(投資用物件)やオーナーチェンジ物件の買取に強い会社はどこ?
買取で高く売却するには、複数社に査定を依頼して高く買ってくれる会社を見つけることが最大のコツです。 買取会社は必ずしもすべての会社が収益物件を扱っているわけではありません。 査定を依頼する

大阪で収益物件(投資用物件)やオーナーチェンジ物件の買取に強い会社はどこ?
収益物件を買取で高く売却するには、複数社に査定を依頼してできるだけ高く買ってくれる会社を見つけだすことがコツです。 そのためには、大阪にどのような買取会社があるのかを知ることが第一歩となります。